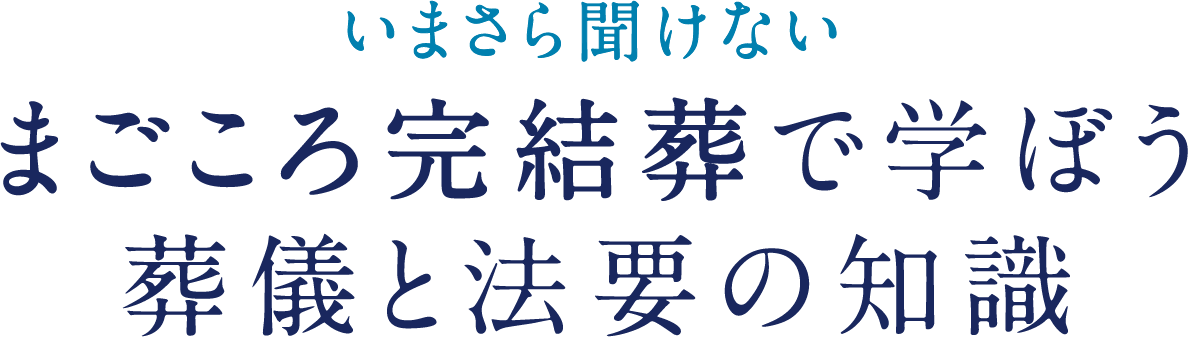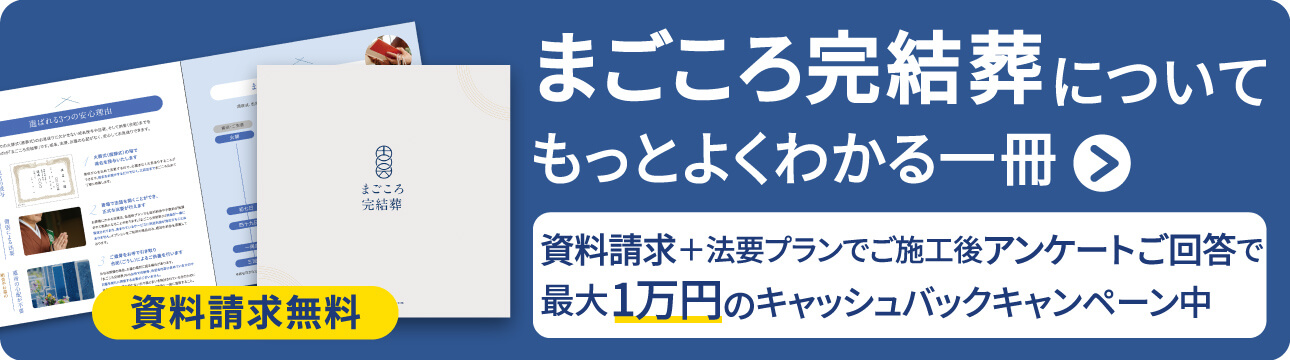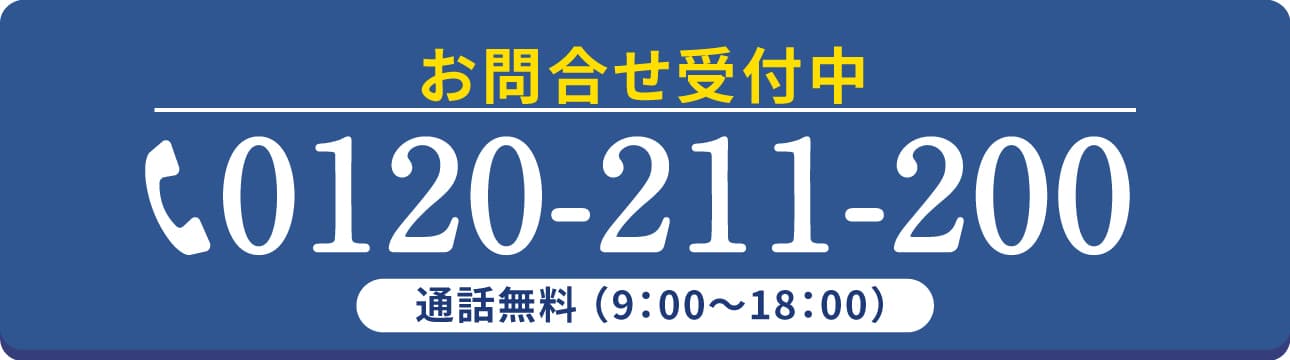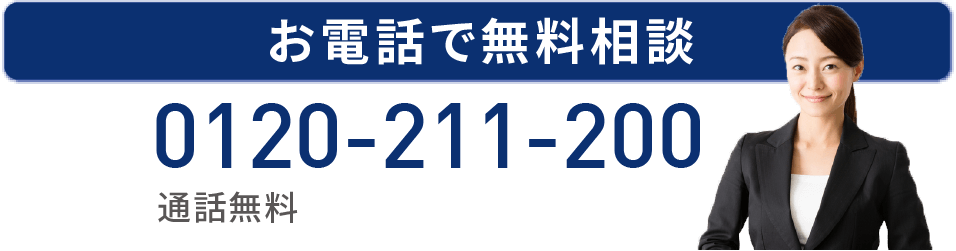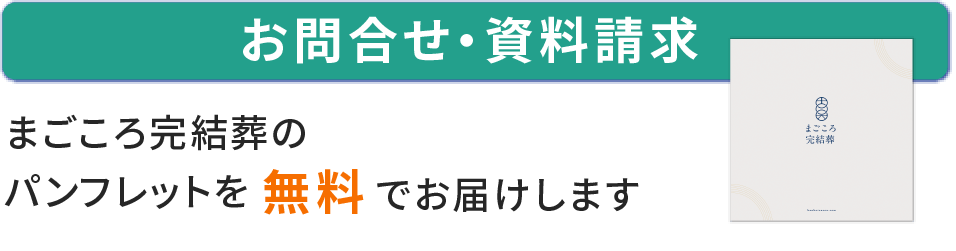法要2021年12月12日
弔問時の服装は平服? 持ち物や線香のマナーも解説
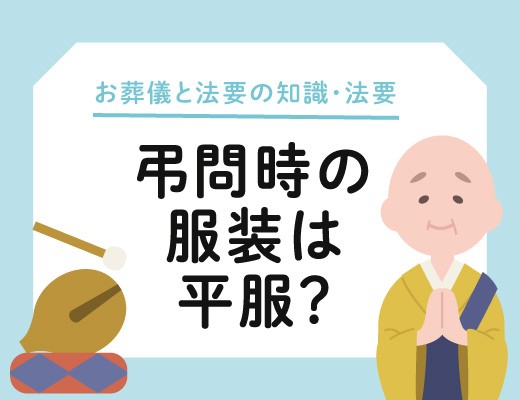
親しかった方の訃報を聞けば、すぐに駆けつけたくなるのが心情です。しかし、遺族の事情を考慮して、訪問すべきかどうか悩む方も多いでしょう。この記事では、お悔やみの言葉を伝える弔問時のマナーをご紹介。遺族を不快にさせないよう覚えておくと安心です。
【もくじ】
1. 弔問時における服装のマナー
弔問とは、訃報を受けてご遺族宅を訪ね、お悔やみの言葉を述べること。通夜や葬儀前、葬儀が終わった後など、訃報を知るタイミングはさまざまですが、いずれの場合でも、遺族の気持ちを汲んだ対応が求められます。弔問時の服装もそのひとつ。弔問する時期や訪問先、故人との関係性など、それぞれの状況に応じた配慮が必要です。まずは、弔問のタイミングを理解して、弔問にふさわしい服装を選びましょう。
●親族
できる限り早く駆けつける。通夜前でも問題なし
●故人と親交の深かった人
できるだけ早く駆けつける。特に親しかった人は通夜前でも構わない
●会社関係者・ご近所
通夜前の弔問を避け、通夜や葬儀に参列。家族葬の場合は葬儀後に弔問する
●親族
できる限り早く駆けつける。通夜前でも問題なし
●故人と親交の深かった人
できるだけ早く駆けつける。特に親しかった人は通夜前でも構わない
●会社関係者・ご近所
通夜前の弔問を避け、通夜や葬儀に参列。家族葬の場合は葬儀後に弔問する
1-1. 【通夜前・葬儀前】喪服を避けて平服を選ぶ
通夜前、葬儀前の弔問は、訃報を受けてすぐに駆けつけたという意味を持ちます。ですから、喪服で訪問すると不幸を予見していたように捉えられかねません。ですから、遺族の気持ちを考えて、地味目の平服を選びましょう。ラフな格好や派手なデザイン、露出の多い服装はNG。外出先から駆けつける場合でも、落ち着いた色合いの服装を着用するのが賢明です。
1-2. 【葬儀後】フォーマルな服装を選ぶ
葬儀後の弔問も、喪服を避けるのが基本です。ただし、葬儀後の弔問は通夜前とは意味合いが異なり、事前に遺族と日程を調整して伺う場合がほとんどです。前もって弔問することがわかっているので、たとえ平服であってもフォーマルな服装を選びましょう。弔問で大切なのは、遺族感情に配慮する心遣いです。
1-3. 男女ともにシンプルな服装を選ぶ
一言で平服といわれても、どのような服装を選べばよいか判断に困る人も多いでしょう。ここでは、弔問にふさわしい服装を男女別にご紹介します。
●男性の服装
ダークスーツに白のワイシャツが基本です。スーツは地模様のない無地のもの。白であってもボタンダウンのワイシャツは避けましょう。ネクタイは無地で光沢のないダークカラー、靴下は黒無地が基本です。足元も光沢のない黒の革靴を合わせましょう。
●女性の服装
女性は平服の略喪服を着用するのが一般的。略喪服とは、ブラックフォーマル以外の黒、紺、グレーといった地味な色合いのワンピースやスーツを指します。アクサリーは真珠が基本。結婚指輪は許容範囲ですが、その他は外すのが無難です。革製品は殺生をイメージさせるので、シンプルな合成素材のカバンや靴を選びます。華美なネイルはNG。薄手の化粧を心がけ、長髪の場合はヘアスタイルもすっきりまとめておきましょう。
●男性の服装
ダークスーツに白のワイシャツが基本です。スーツは地模様のない無地のもの。白であってもボタンダウンのワイシャツは避けましょう。ネクタイは無地で光沢のないダークカラー、靴下は黒無地が基本です。足元も光沢のない黒の革靴を合わせましょう。
●女性の服装
女性は平服の略喪服を着用するのが一般的。略喪服とは、ブラックフォーマル以外の黒、紺、グレーといった地味な色合いのワンピースやスーツを指します。アクサリーは真珠が基本。結婚指輪は許容範囲ですが、その他は外すのが無難です。革製品は殺生をイメージさせるので、シンプルな合成素材のカバンや靴を選びます。華美なネイルはNG。薄手の化粧を心がけ、長髪の場合はヘアスタイルもすっきりまとめておきましょう。
2. 弔問時における持ち物のマナー
弔問時は、服装だけでなく持ち物にも注意を払いましょう。弔問のタイミングによって要否が違うものもありますので、以下の例を参考に、自分の状況に当てはめて対応することをおすすめします。
2-1. 通夜前・葬儀前の弔問時
基本的に通夜・葬儀前のお供えは不要です。どうしても渡すなら、通夜開始まで故人の枕元を飾る枕花や、通夜・葬儀の会場を彩る供花を準備するとよいでしょう。ただし、事前に遺族の意向を確認してから用意するのが順当です。供花は通夜の開始に間に合うよう、余裕を見て手配します。
また、通夜前の弔問に香典は必要ありません。取り急ぎ駆けつけるという意味合いがあるため、持参すると失礼にあたるとも考えられます。
また、通夜前の弔問に香典は必要ありません。取り急ぎ駆けつけるという意味合いがあるため、持参すると失礼にあたるとも考えられます。
2-2. 葬儀後の持ち物
葬儀後の弔問で香典を持参するのは、通夜や葬儀に参列できなかった場合のみ。お悔やみを述べるときに差し出すのが一般的です。故人の好きだったお菓子や果物など、お供えを持参するのは構いませんが、品物によってはお供えに適さないこともあります。中身の個数にも注意が必要で、「4」「9」といった不幸を連想させる数は避けましょう。
いずれの場合も、遺族がお供えや香典を遠慮するケースがあります。たとえ善意でも遺族の意向を無視した言動は慎みましょう。
いずれの場合も、遺族がお供えや香典を遠慮するケースがあります。たとえ善意でも遺族の意向を無視した言動は慎みましょう。
3. 弔問時における線香のマナー
線香をあげる行為には、3つの由来があります。
・故人の食べ物として
・自分の身を清めるため
・故人と心を通わせるため
込められた意味を心に留め置いて線香をあげたら、故人を偲んで静かに手を合わせましょう。
弔問先の仏壇に線香をあげる際のマナーも紹介します。宗派による違いがあるため、事前に宗派を確認しておくと安心です。
●天台宗・真言宗
線香の数は3本。同時に火をつけて、手前1本、奥に2本と逆三角形になるよう香炉に立てる
●浄土宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗
線香の数は1本。線香に火をつけて、香炉の真ん中に立てる
●浄土真宗本願寺派
線香の数は1本。線香を2つに折り、同時に火をつける。火が左になるよう香炉に寝かせる。
●真宗大谷派
線香の数は1~2本。線香1~2本を2つに折り、同時に火をつける。火を左にして香炉に寝かせ置く
宗派に限らず、線香はロウソクの火を移してつけるのが作法です。まずロウソクに火を灯してから線香に火をつけましょう。また、火のついた線香に直接息を吹きかけるのはマナー違反。線香を持っていない方の手で扇いで消しましょう。
・故人の食べ物として
・自分の身を清めるため
・故人と心を通わせるため
込められた意味を心に留め置いて線香をあげたら、故人を偲んで静かに手を合わせましょう。
弔問先の仏壇に線香をあげる際のマナーも紹介します。宗派による違いがあるため、事前に宗派を確認しておくと安心です。
●天台宗・真言宗
線香の数は3本。同時に火をつけて、手前1本、奥に2本と逆三角形になるよう香炉に立てる
●浄土宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗
線香の数は1本。線香に火をつけて、香炉の真ん中に立てる
●浄土真宗本願寺派
線香の数は1本。線香を2つに折り、同時に火をつける。火が左になるよう香炉に寝かせる。
●真宗大谷派
線香の数は1~2本。線香1~2本を2つに折り、同時に火をつける。火を左にして香炉に寝かせ置く
宗派に限らず、線香はロウソクの火を移してつけるのが作法です。まずロウソクに火を灯してから線香に火をつけましょう。また、火のついた線香に直接息を吹きかけるのはマナー違反。線香を持っていない方の手で扇いで消しましょう。
4. 弔問時に遺族を傷つけない挨拶・言葉遣いのマナー
お悔やみの挨拶や言葉遣いも弔事におけるマナーのひとつ。特に「忌み言葉」には注意が必要です。忌み言葉とは不吉な言葉のこと。死や苦を連想させる数字の「4」や「9」も忌み言葉の一種です。
・重ね言葉
重ね言葉は文字通り、同じ言葉を重ねること。不幸が続くことを連想させるためお悔やみにはふさわしくありません。「次々」「返す返す」「重ね重ね」「いよいよ」などがこれにあたります。
・生死に関する直接的な言葉
「死ぬ」「急死」「生きていた」など、命に関わる直接的な表現も避けましょう。
・宗教によっては避けるべき言葉
日本の葬儀は仏式がほとんどです。
仏教の忌み言葉は共通と思われがちですが、実は宗派によって違いがあります。
例えば、「冥福を祈る」は、冥土を彷徨うという概念のない浄土真宗では使いません。
多くの宗教や宗派でも使える「お悔やみ申し上げます」と言い換えるのが良いでしょう。
・神道における忌み言葉
お悔やみの言葉としてよく耳にする「往生」「供養」「成仏」も仏教用語。死生観の異なる神道では使えません。
・キリスト教における忌み言葉
キリスト教では「人の死」は「永遠の命の始まり」とされているため、神道と同じく「成仏」「供養」「冥福」「往生」は不向きです。故人の死を悼む「お悔やみ」という言葉もふさわしくありません。
・重ね言葉
重ね言葉は文字通り、同じ言葉を重ねること。不幸が続くことを連想させるためお悔やみにはふさわしくありません。「次々」「返す返す」「重ね重ね」「いよいよ」などがこれにあたります。
・生死に関する直接的な言葉
「死ぬ」「急死」「生きていた」など、命に関わる直接的な表現も避けましょう。
・宗教によっては避けるべき言葉
日本の葬儀は仏式がほとんどです。
仏教の忌み言葉は共通と思われがちですが、実は宗派によって違いがあります。
例えば、「冥福を祈る」は、冥土を彷徨うという概念のない浄土真宗では使いません。
多くの宗教や宗派でも使える「お悔やみ申し上げます」と言い換えるのが良いでしょう。
・神道における忌み言葉
お悔やみの言葉としてよく耳にする「往生」「供養」「成仏」も仏教用語。死生観の異なる神道では使えません。
・キリスト教における忌み言葉
キリスト教では「人の死」は「永遠の命の始まり」とされているため、神道と同じく「成仏」「供養」「冥福」「往生」は不向きです。故人の死を悼む「お悔やみ」という言葉もふさわしくありません。
4-1. 配慮に欠けた「励ましの言葉」は遺族を傷つけることも
宗教や宗派に関わらず控えるべきは、安易な励ましです。悲しみの真っ只中にいる遺族の様子を目の当たりにすると、つい励ましたいという気持ちになりますが、家族を亡くしてすぐの遺族にとっては、負担になりかねません。「頑張って」「元気を出して」と声をかけるのではなく、「お辛いこととお察しいたします」「お力落としのことと存じます」など、遺族の気持ちに寄り添った、控えめな言葉を選びましょう。
まとめ
弔問時の服装を中心に、守るべきマナーをまとめました。
家族を亡くしてすぐの遺族は悲しみに暮れています。そんな気持ちを察して、相手を傷つけない配慮が必要です。遺族に立場に立って物事を考える。ちょっとした気遣いが弔問時のマナーにつながります。
家族を亡くしてすぐの遺族は悲しみに暮れています。そんな気持ちを察して、相手を傷つけない配慮が必要です。遺族に立場に立って物事を考える。ちょっとした気遣いが弔問時のマナーにつながります。