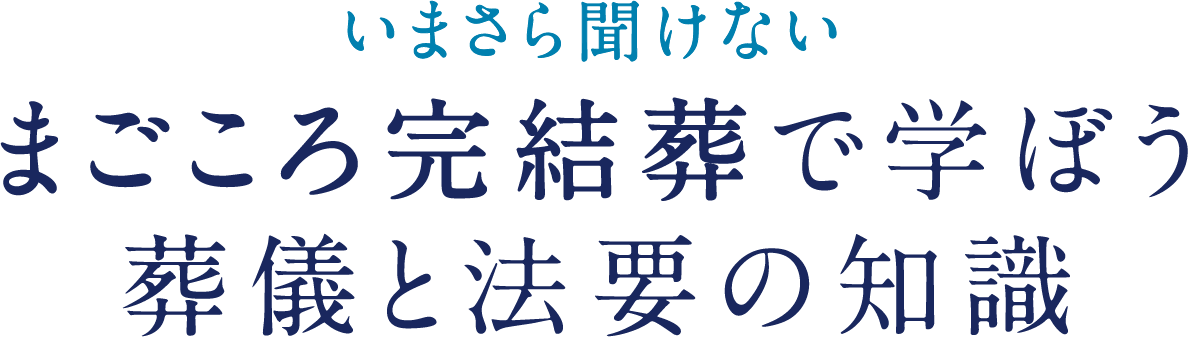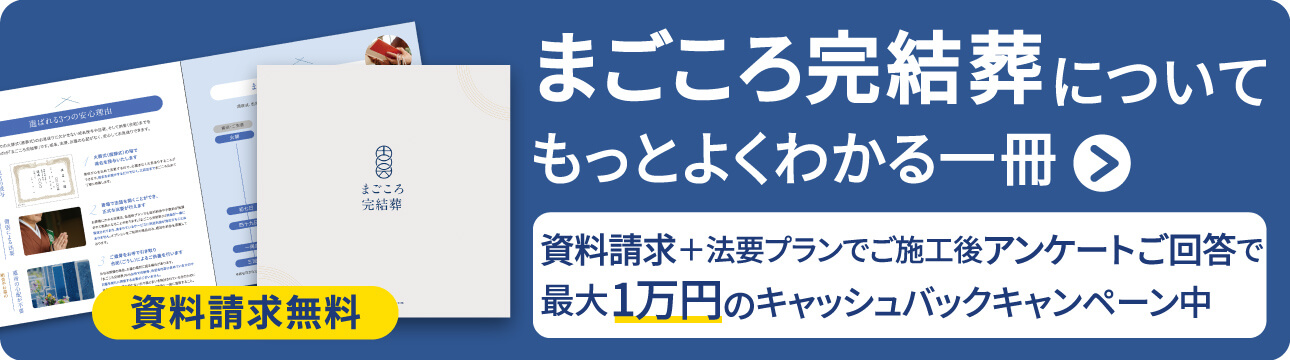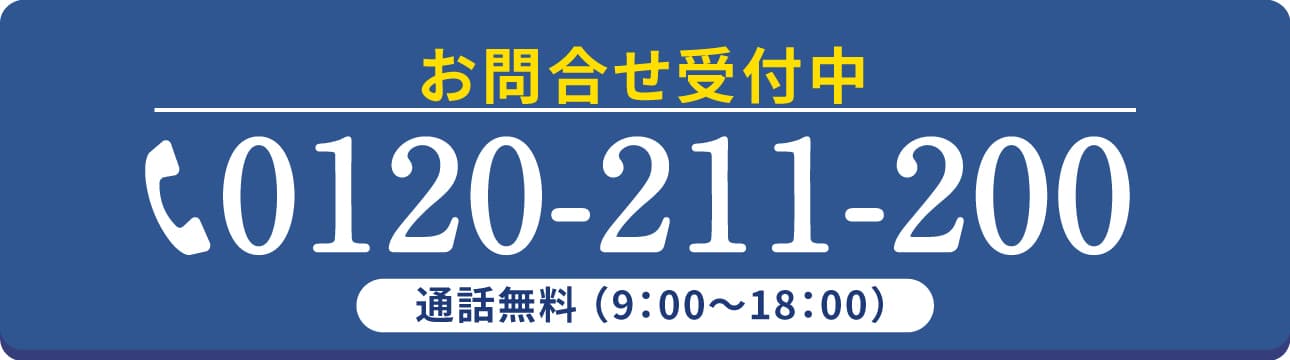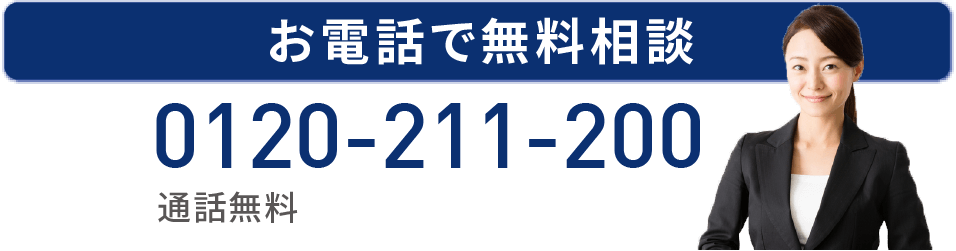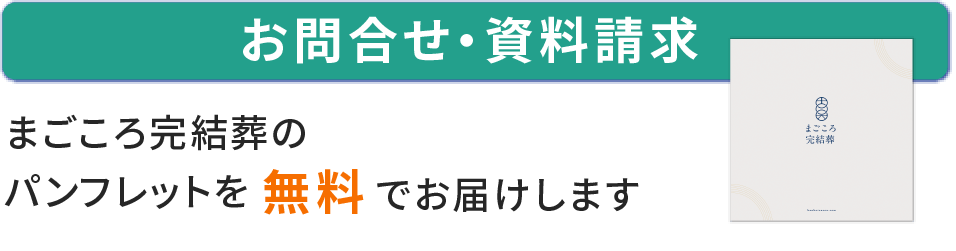法要2021年11月03日
般若心経の全文・読み方を紹介|意味や宗派による違いも
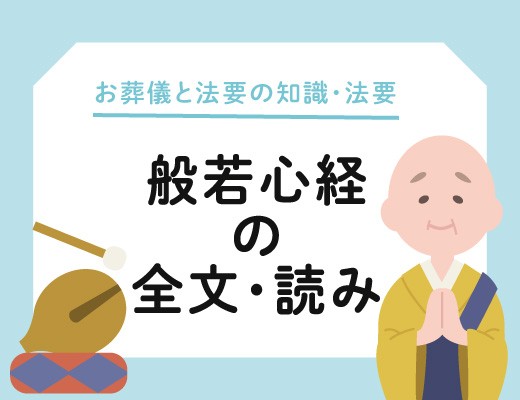
般若心経は法要や葬儀で聞く機会が多いものの、全文の意味を理解している人は少ないでしょう。般若心経の内容や意味を理解すれば、より心を込めた故人やご先祖の供養を行えます。本記事では般若心経の全文の内容や日本語訳、そこで語られている意味について解説します。
【もくじ】
1. 般若心経とは|全文・読み方を紹介
般若心経とは、仏教のお経のひとつです。日本では真言宗、天台宗、禅宗、法相宗など複数の宗派で用いられていて、葬儀や法要で聞く機会が多いことから、数あるお経の中でも最も有名なものといえます。
一方で、「はんにゃしんきょう」(正しくは「はんにゃしんぎょう」)と間違えて覚えている方が多いように、知名度のわりにはその内容や意味まで知っている人は多くありません。
般若心経は、正式名を「般若波羅密多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」といい、インドのサンスクリット語では「プラジュニャーパーラミター・フリダヤ」と呼ばれます。その特徴は、260文字(説によっては262文字)という短い文章の中で、大乗仏教の根幹ともいえる「空」と「般若」の思想が説かれていていること。また、語り口の親しみやすさ、わかりやすさから、現在では宗教や宗派に関わらず、多くの人がその内容に共感しています。
日本に入ってきた般若心経は漢語訳されたもので、8種類あるとされます。その中で最も広く普及している玄奘訳の般若心経を紹介します。
仏説摩訶般若波羅蜜多心経
ぶっせつまか はんにゃはらみったしんぎょう
観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時
かんじざいぼさつ ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空 度一切苦厄
しょうけんごうんかいくう どいっさいくやく
舎利子 色不異空 空不異色
しゃりし しきふいくう くうふいしき
色即是空 空即是色
しきそくぜくう くうそくぜしき
受想行識 亦復如是
じゅそうぎょうしき やくぶにょぜ
舎利子 是諸法空相
しゃりし ぜしょほうくうそう
不生不滅 不垢不浄 不増不減
ふしょうふめつ ふくふじょう ふぞうふげん
是故空中 無色無受想行識
ぜこくうちゅう むしきむじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法
むげんにびぜっしんに にしきしょうこうみそくほう
無眼界 乃至無意識界
むげんかい ないしむいしきかい
無無明 亦無無明尽
むむみょう やくむむみょうじん
乃至無老死 亦無老死尽
ないしむろうし やくむろうしじん
無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故
むくしゅうめつどう むちやくむとく いむしょとくこ
菩提薩埵 依般若波羅蜜多故
ぼだいさった えはんにゃはらみったこ
心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖
しんむけいげ むけいげこ むうくふ
遠離一切顚倒夢想 究竟涅槃
おんりいっさいてんどうむそう くきょうねはん
三世諸仏 依般若波羅蜜多故
さんぜしょぶつ えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提
とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多
こちはんにゃはらみった
是大神呪 是大明呪
ぜだいじんしゅ ぜだいみょうしゅ
是無上呪 是無等等呪
ぜむじょうしゅ ぜむとうどうしゅ
能除一切苦 真実不虚
のうじょいっさいく しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪
こせつはんにゃはらみったしゅ
即説呪日
そくせつしゅわつ
羯帝 羯帝 波羅羯帝 波羅僧羯帝
ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそうぎゃてい
菩提僧莎訶
ぼうじそわか
般若心経
はんにゃしんぎょう
(引用:NHKサービスセンター「仏説摩訶般若波羅蜜多心経より)
一方で、「はんにゃしんきょう」(正しくは「はんにゃしんぎょう」)と間違えて覚えている方が多いように、知名度のわりにはその内容や意味まで知っている人は多くありません。
般若心経は、正式名を「般若波羅密多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」といい、インドのサンスクリット語では「プラジュニャーパーラミター・フリダヤ」と呼ばれます。その特徴は、260文字(説によっては262文字)という短い文章の中で、大乗仏教の根幹ともいえる「空」と「般若」の思想が説かれていていること。また、語り口の親しみやすさ、わかりやすさから、現在では宗教や宗派に関わらず、多くの人がその内容に共感しています。
日本に入ってきた般若心経は漢語訳されたもので、8種類あるとされます。その中で最も広く普及している玄奘訳の般若心経を紹介します。
仏説摩訶般若波羅蜜多心経
ぶっせつまか はんにゃはらみったしんぎょう
観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時
かんじざいぼさつ ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空 度一切苦厄
しょうけんごうんかいくう どいっさいくやく
舎利子 色不異空 空不異色
しゃりし しきふいくう くうふいしき
色即是空 空即是色
しきそくぜくう くうそくぜしき
受想行識 亦復如是
じゅそうぎょうしき やくぶにょぜ
舎利子 是諸法空相
しゃりし ぜしょほうくうそう
不生不滅 不垢不浄 不増不減
ふしょうふめつ ふくふじょう ふぞうふげん
是故空中 無色無受想行識
ぜこくうちゅう むしきむじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法
むげんにびぜっしんに にしきしょうこうみそくほう
無眼界 乃至無意識界
むげんかい ないしむいしきかい
無無明 亦無無明尽
むむみょう やくむむみょうじん
乃至無老死 亦無老死尽
ないしむろうし やくむろうしじん
無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故
むくしゅうめつどう むちやくむとく いむしょとくこ
菩提薩埵 依般若波羅蜜多故
ぼだいさった えはんにゃはらみったこ
心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖
しんむけいげ むけいげこ むうくふ
遠離一切顚倒夢想 究竟涅槃
おんりいっさいてんどうむそう くきょうねはん
三世諸仏 依般若波羅蜜多故
さんぜしょぶつ えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提
とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多
こちはんにゃはらみった
是大神呪 是大明呪
ぜだいじんしゅ ぜだいみょうしゅ
是無上呪 是無等等呪
ぜむじょうしゅ ぜむとうどうしゅ
能除一切苦 真実不虚
のうじょいっさいく しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪
こせつはんにゃはらみったしゅ
即説呪日
そくせつしゅわつ
羯帝 羯帝 波羅羯帝 波羅僧羯帝
ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそうぎゃてい
菩提僧莎訶
ぼうじそわか
般若心経
はんにゃしんぎょう
(引用:NHKサービスセンター「仏説摩訶般若波羅蜜多心経より)
1-1. 般若心経の由来と歴史
般若心経は仏教の経典のひとつです。経典とは、釈迦の教えを文章にしたものです。
そもそも仏教の開祖である釈迦は、自らの教えを口伝で弟子に伝えていました。しかし、それでは歳月とともに弟子たちの間で解釈の違いが生じます。それではいけないということで、弟子たちは釈迦の教え(仏典)を、「経(教え)」、「律(戒め)」、「論(道理)」の3種類に整理しました。般若心経をはじめとする「お経」は、この「経(教え)」に属します。
般若心経の由来は、西遊記で三蔵法師として知られている玄奘(げんじょう)がインドから中国に持ち帰った「大般若経(だいはんにゃきょう)」と言われます。玄奘は西暦629年から西暦645年にかけてインドを旅し、帰国後は76部1347巻という数のお経を漢字に翻訳しました。そのひとつが般若心経です。
その後、般若心経は奈良時代から平安時代にかけて日本に渡り、国内で広がっていったとされます。
そもそも仏教の開祖である釈迦は、自らの教えを口伝で弟子に伝えていました。しかし、それでは歳月とともに弟子たちの間で解釈の違いが生じます。それではいけないということで、弟子たちは釈迦の教え(仏典)を、「経(教え)」、「律(戒め)」、「論(道理)」の3種類に整理しました。般若心経をはじめとする「お経」は、この「経(教え)」に属します。
般若心経の由来は、西遊記で三蔵法師として知られている玄奘(げんじょう)がインドから中国に持ち帰った「大般若経(だいはんにゃきょう)」と言われます。玄奘は西暦629年から西暦645年にかけてインドを旅し、帰国後は76部1347巻という数のお経を漢字に翻訳しました。そのひとつが般若心経です。
その後、般若心経は奈良時代から平安時代にかけて日本に渡り、国内で広がっていったとされます。
1-2. 宗派によって異なるお経
お経の代名詞的存在の般若心経ですが、実は同じ仏教でも宗派によっては読まれません。般若心経の代わりに別の経典が用いられます。特に浄土真宗と日蓮宗では般若心経を読むこともありません。
浄土真宗は日本でも多くの信者を抱える仏教宗派です。浄土真宗では、「阿弥陀仏(阿弥陀如来)」の本願によって往生できると考えられています。簡単にいうと、阿弥陀仏の力(他力)を信じることで極楽浄土に達せられるというわけです。そのため、自らの悟り(自力)での往生を説く般若心経は、教義が異ります。浄土真宗で重要とされるお経は「大無量寿経」、「観無量寿経」、「阿弥陀経」の3種類です。
日蓮宗では、「法華経」こそが真実の教えだと考えられています。そのため日蓮宗では般若心経に限らず、法華経以外のお経が唱えられたり、写経などに用いられることはありません。
浄土真宗は日本でも多くの信者を抱える仏教宗派です。浄土真宗では、「阿弥陀仏(阿弥陀如来)」の本願によって往生できると考えられています。簡単にいうと、阿弥陀仏の力(他力)を信じることで極楽浄土に達せられるというわけです。そのため、自らの悟り(自力)での往生を説く般若心経は、教義が異ります。浄土真宗で重要とされるお経は「大無量寿経」、「観無量寿経」、「阿弥陀経」の3種類です。
日蓮宗では、「法華経」こそが真実の教えだと考えられています。そのため日蓮宗では般若心経に限らず、法華経以外のお経が唱えられたり、写経などに用いられることはありません。
2. 【要約版】般若心経の現代日本語訳
ここでは般若心経を現代の日本人でもわかるように訳します。
その前に、原文に頻繁に登場する「舎利子」について説明しましょう。舎利子とは、釈迦の弟子であるシャーリプトラのことです。彼に釈迦が語りかける形で般若心経は進みます。
なお、舎利子は釈迦の十大弟子の一人に数えられる人物です。いわば舎利子を優れた弟子と見込んで、教えを説いているわけです。
観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時
照見五蘊皆空 度一切苦厄
まずお釈迦様は「観音菩薩は修行される中で、この世を形づくるあらゆるもの・こと(五蘊)は皆、『空(くう)』であると悟られた」と話し始めます。
舎利子 色不異空 空不異色
色即是空 空即是色
受想行識 亦復如是
舎利子 是諸法空相
不生不滅 不垢不浄 不増不減
「舎利子よ、目に見えるもの(色)も含めてこの世のあらゆるものには実体がない(空)。人の肉体も感覚でも同じである。実体がなければ生まれることも、消えることも、汚れたり清らかになることも、増えたり減ったりすることもないのだ」
是故空中 無色無受想行識
無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法
無眼界 乃至無意識界
無無明 亦無無明尽
乃至無老死 亦無老死尽
無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故
菩提薩埵 依般若波羅蜜多故
心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖
遠離一切顚倒夢想 究竟涅槃
三世諸仏 依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提
ここでお釈迦様は「空」について詳しく説きます。それを要約すると次のようになります。
「人間が感じたり考えたりすること、悩みや苦しみも、実は存在しない。それでも老いや死は避けられないし、悩みや苦しみも尽きることがない。だがそれらの解決はできないし、その方法を知ることもできない。だったらこだわるのをやめよう。欲望から離れることで悟りを得て、涅槃(煩悩から解脱した境地)へと至ることができるのだ」
故知般若波羅蜜多
是大神呪 是大明呪
是無上呪 是無等等呪
能除一切苦 真実不虚
故説般若波羅蜜多呪
即説呪日
ここからお釈迦様は、「仏の智慧(ちえ)は偉大である」と語ります。「仏の智慧は真実であり、何かと比べることもできない。一切の苦しみを取り除く、偽りのないものである。そして、その智慧をわかりやすく言うと、次の通りである」
羯帝 羯帝 波羅羯帝 波羅僧羯帝
菩提僧莎訶
「往け、往け、彼の岸へ。いざともに渡ろう。幸あらん」
この「ぎゃーてーぎゃーてー」から始まる一節は、様々に現代語訳されています。わかりやすくいえば、「彼岸(悟りによって開かれる安楽の場所)」を皆で目指そう」と、人々を鼓舞するメッセージなのでしょう。
その前に、原文に頻繁に登場する「舎利子」について説明しましょう。舎利子とは、釈迦の弟子であるシャーリプトラのことです。彼に釈迦が語りかける形で般若心経は進みます。
なお、舎利子は釈迦の十大弟子の一人に数えられる人物です。いわば舎利子を優れた弟子と見込んで、教えを説いているわけです。
観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時
照見五蘊皆空 度一切苦厄
まずお釈迦様は「観音菩薩は修行される中で、この世を形づくるあらゆるもの・こと(五蘊)は皆、『空(くう)』であると悟られた」と話し始めます。
舎利子 色不異空 空不異色
色即是空 空即是色
受想行識 亦復如是
舎利子 是諸法空相
不生不滅 不垢不浄 不増不減
「舎利子よ、目に見えるもの(色)も含めてこの世のあらゆるものには実体がない(空)。人の肉体も感覚でも同じである。実体がなければ生まれることも、消えることも、汚れたり清らかになることも、増えたり減ったりすることもないのだ」
是故空中 無色無受想行識
無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法
無眼界 乃至無意識界
無無明 亦無無明尽
乃至無老死 亦無老死尽
無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故
菩提薩埵 依般若波羅蜜多故
心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖
遠離一切顚倒夢想 究竟涅槃
三世諸仏 依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提
ここでお釈迦様は「空」について詳しく説きます。それを要約すると次のようになります。
「人間が感じたり考えたりすること、悩みや苦しみも、実は存在しない。それでも老いや死は避けられないし、悩みや苦しみも尽きることがない。だがそれらの解決はできないし、その方法を知ることもできない。だったらこだわるのをやめよう。欲望から離れることで悟りを得て、涅槃(煩悩から解脱した境地)へと至ることができるのだ」
故知般若波羅蜜多
是大神呪 是大明呪
是無上呪 是無等等呪
能除一切苦 真実不虚
故説般若波羅蜜多呪
即説呪日
ここからお釈迦様は、「仏の智慧(ちえ)は偉大である」と語ります。「仏の智慧は真実であり、何かと比べることもできない。一切の苦しみを取り除く、偽りのないものである。そして、その智慧をわかりやすく言うと、次の通りである」
羯帝 羯帝 波羅羯帝 波羅僧羯帝
菩提僧莎訶
「往け、往け、彼の岸へ。いざともに渡ろう。幸あらん」
この「ぎゃーてーぎゃーてー」から始まる一節は、様々に現代語訳されています。わかりやすくいえば、「彼岸(悟りによって開かれる安楽の場所)」を皆で目指そう」と、人々を鼓舞するメッセージなのでしょう。
3. 般若心経の中心思想「空」とは
般若心経の核心といえる「空」は、仏教においても重要な教えのひとつとされます。その意味は、「この世のあらゆるものは、絶対的に存在するものではない」ということです。たとえばテストで1位を取った人も、2位や3位の人がいるから1位であり、相対的な存在です。悪人と呼ばれる人も、ある人からすればもしかすると良い人かもしれません。
聖なるものも、俗なるものの存在があって聖になり、俗なるものも聖なるものが存在するから俗になる。このように、何物にも依存せずに存在する(自性;じしょう)ものがないことを、「空」といいます。
「空」の解釈は人によってさまざまに異なります。しかし、この世にあるものすべてが「空」、つまり相対的に存在するものだとしたら、「空」そのものも相対的なものですから、人によって解釈が異なるのも当然といえます。いずれにせよ、「この人は悪い人だ」「自分は恵まれていない」といったネガティブな思考や、あらよる欲望への執着から解放され、物事は相対的に変化するものであると考える「空」は、人生をより自然体で生きていくための大切なヒントになるでしょう。
聖なるものも、俗なるものの存在があって聖になり、俗なるものも聖なるものが存在するから俗になる。このように、何物にも依存せずに存在する(自性;じしょう)ものがないことを、「空」といいます。
「空」の解釈は人によってさまざまに異なります。しかし、この世にあるものすべてが「空」、つまり相対的に存在するものだとしたら、「空」そのものも相対的なものですから、人によって解釈が異なるのも当然といえます。いずれにせよ、「この人は悪い人だ」「自分は恵まれていない」といったネガティブな思考や、あらよる欲望への執着から解放され、物事は相対的に変化するものであると考える「空」は、人生をより自然体で生きていくための大切なヒントになるでしょう。
4. 葬儀・法要における般若心経の役割
般若心経は仏教に関する行事で読まれることが多くあります。葬儀や法要がその代表です。ただし、先述の通り真言宗や日蓮宗で読まれることはなく、またそのほかの宗派でも別のお経が読まれることもあります。
葬祭で般若心経が読まれるタイミングは、通夜や納棺前、火葬場であることが多く、葬儀式で唱えられることはまれです。もっとも、宗派やお坊さんによってタイミングは異なります。
般若心経の役割は、葬儀と法要で少し違いがあります。葬儀では故人の冥福を祈ることが主な目的です、一方、法要では、般若心経を唱えることで積める「徳」を故人に回し向けるため、すなわち「回向(えこう)」として行います。
葬祭で般若心経が読まれるタイミングは、通夜や納棺前、火葬場であることが多く、葬儀式で唱えられることはまれです。もっとも、宗派やお坊さんによってタイミングは異なります。
般若心経の役割は、葬儀と法要で少し違いがあります。葬儀では故人の冥福を祈ることが主な目的です、一方、法要では、般若心経を唱えることで積める「徳」を故人に回し向けるため、すなわち「回向(えこう)」として行います。
まとめ
般若心経の全文や現代語訳、由来や意味について解説しました。般若心経の教えは、仏教の長い歴史の中でも色褪せることなく、現代に生きる私たちに深い気付きを与えてくれます。般若心経に込められた意味を理解することで、より心のこもった供養を行えます。