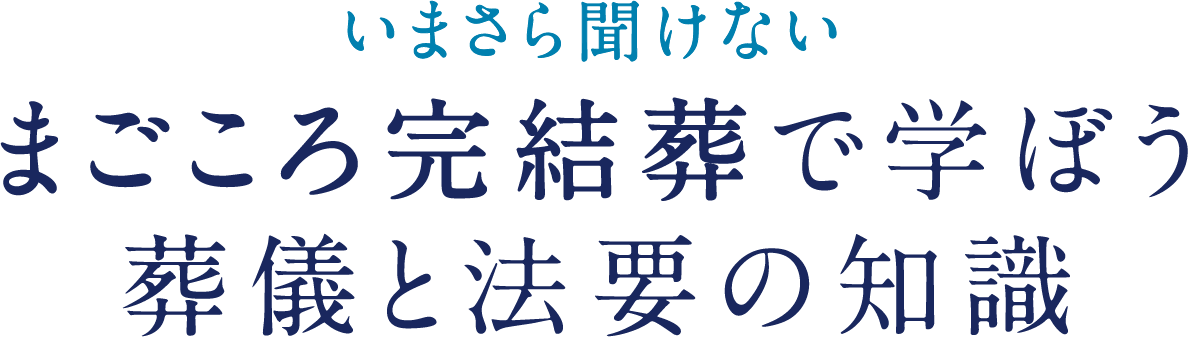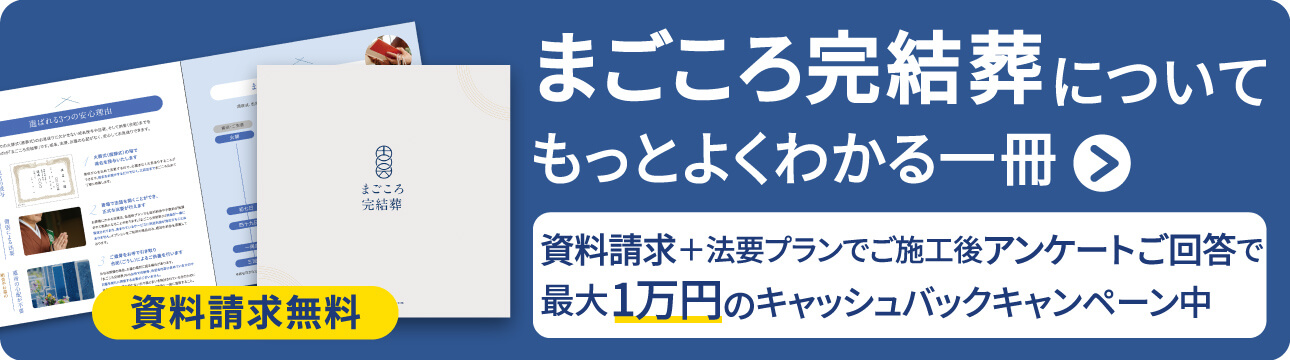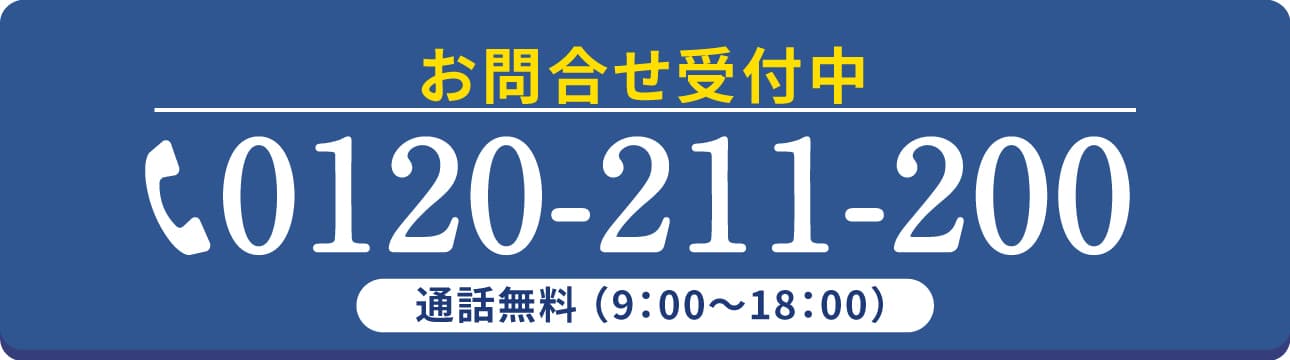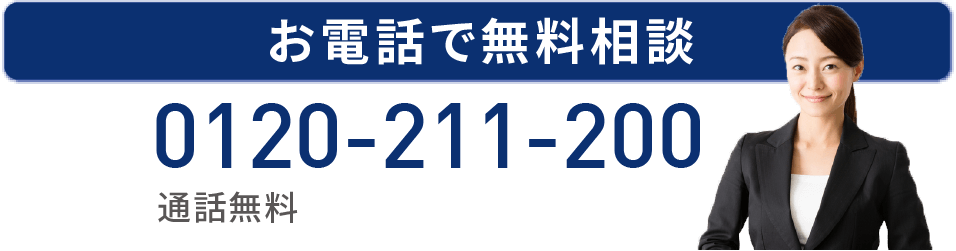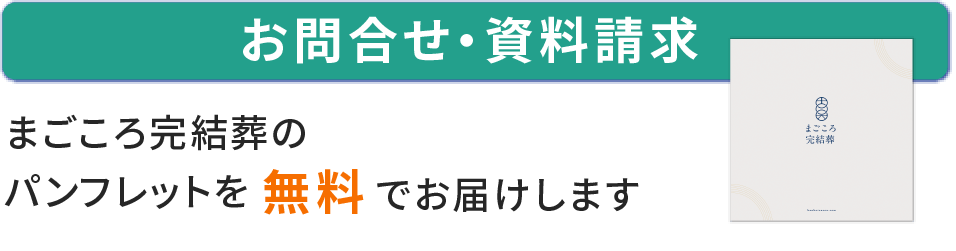法要2021年02月18日
直葬とは? 執り行う前に知りたいマナーやメリットを解説
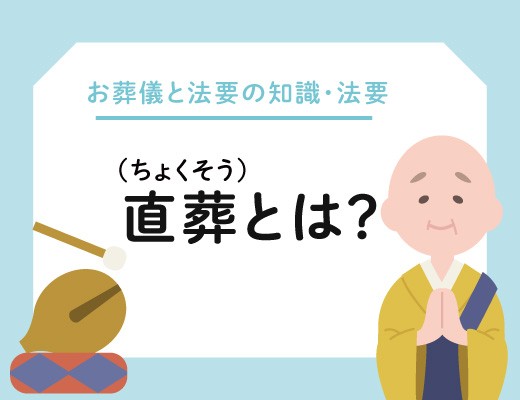
通夜や告別式を行わない「直葬」を選ぶ人が増えています。では直葬には、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。故人と納得できる形でお別れしたい方や、自分の仕事や家族に経済的な負担をかけたくないと考えている方に、直葬の基本を紹介します。
【もくじ】
1. 直葬とは?
直葬とは、通夜・告別式を行わず、火葬のみで故人をお見送りすることです。火葬式とも呼ばれます。通夜・告別式を行う従来式の葬儀に対して必要性を感じない人から注目され、執り行われる件数も年々増加しています。
新しい葬儀として一般的に知られるようになった直葬ですが、実は直葬そのものは昔から存在しました。経済的な理由で葬儀を挙げることができない人や身寄りのない人のために、葬儀業者がプラン外の葬儀として行っていたのです。「直葬」という言葉も、元々は葬儀業者の間で使用される業界用語でした。
その直葬が一般的に知られるようになった理由には、日本人の宗教観や核家族化に伴う人間関係の変化が挙げられます。近所付き合いも減った現代では、これまでのように多くの人を招いて通夜・告別式を行う意味は薄れつつあります。また、昨今のコロナ禍で、三密を避けるために直葬を選ぶ人も増えました。
新しい葬儀として一般的に知られるようになった直葬ですが、実は直葬そのものは昔から存在しました。経済的な理由で葬儀を挙げることができない人や身寄りのない人のために、葬儀業者がプラン外の葬儀として行っていたのです。「直葬」という言葉も、元々は葬儀業者の間で使用される業界用語でした。
その直葬が一般的に知られるようになった理由には、日本人の宗教観や核家族化に伴う人間関係の変化が挙げられます。近所付き合いも減った現代では、これまでのように多くの人を招いて通夜・告別式を行う意味は薄れつつあります。また、昨今のコロナ禍で、三密を避けるために直葬を選ぶ人も増えました。
1-1. 直葬の流れ
直葬の流れは、通夜・告別式が省略されるだけで、あとは一般の葬儀と同じです。
直葬の流れ
【臨終】 医師に死亡診断書を発行してもらい、葬儀業者を手配する。
【安置】 火葬ができるようになるまで、故人を安置する。
【納棺・出棺】 故人を棺へ納める。
【火葬】 火葬場へ故人を移動させ、荼毘に付す。
【骨上げ】 火葬後の遺骨を骨壷に納める。
直葬の流れ
【臨終】 医師に死亡診断書を発行してもらい、葬儀業者を手配する。
【安置】 火葬ができるようになるまで、故人を安置する。
【納棺・出棺】 故人を棺へ納める。
【火葬】 火葬場へ故人を移動させ、荼毘に付す。
【骨上げ】 火葬後の遺骨を骨壷に納める。
2. 直葬のメリット・デメリット
実際に直葬を行った場合のメリット・デメリットを紹介します。
メリットとしてまず挙げられるのは、故人の遺志や遺族の想いを優先したお見送りができることです。直葬は基本的に近親者のみで執り行うため、参列者や弔問客への対応に心を配る必要がありません。世間体を気にすることなく、故人とのお別れに向き合うことができます。
続いてのメリットは、経済的に少ない負担でお見送りができることです。参列者や弔問客がいないため、通夜ぶるまいや精進落としといった料理や火葬場までのマイクロバスなどの手配をする必要はなく、それに関わる費用も発生しません。香典の受け取りを辞退すれば、会葬御礼や香典返しなどの返礼品も不要です。
一般的な葬儀では、約200万円が必要とされますが、直葬は約20万円で行えます。10分の1ですから、経済的な負担はかなり軽減できるといえるでしょう。
また、時間的な負担を軽減できるのも直葬ならではです。一般的な葬儀では通夜・告別式で2日間かかりますが、直葬ではおよそ半日。火葬場によっては、数時間で終えることも可能です。
近親者のみで行う規模の小ささが直葬の特長ですが、人によってはそれがデメリットになることもあります。例えば、故人が生前に深くお付き合いしていた方は葬儀に参列したいと考えるでしょうし、また、時間をかけて故人を偲びたいと思う方もいるでしょう。後悔のない直葬にするには、そのような方々からの理解を得ることも重要です。直葬後に、「お別れ会」と称して改めて惜別の機会を設けるなど、参列希望者への配慮も忘れずに行いましょう。
メリットとしてまず挙げられるのは、故人の遺志や遺族の想いを優先したお見送りができることです。直葬は基本的に近親者のみで執り行うため、参列者や弔問客への対応に心を配る必要がありません。世間体を気にすることなく、故人とのお別れに向き合うことができます。
続いてのメリットは、経済的に少ない負担でお見送りができることです。参列者や弔問客がいないため、通夜ぶるまいや精進落としといった料理や火葬場までのマイクロバスなどの手配をする必要はなく、それに関わる費用も発生しません。香典の受け取りを辞退すれば、会葬御礼や香典返しなどの返礼品も不要です。
一般的な葬儀では、約200万円が必要とされますが、直葬は約20万円で行えます。10分の1ですから、経済的な負担はかなり軽減できるといえるでしょう。
また、時間的な負担を軽減できるのも直葬ならではです。一般的な葬儀では通夜・告別式で2日間かかりますが、直葬ではおよそ半日。火葬場によっては、数時間で終えることも可能です。
近親者のみで行う規模の小ささが直葬の特長ですが、人によってはそれがデメリットになることもあります。例えば、故人が生前に深くお付き合いしていた方は葬儀に参列したいと考えるでしょうし、また、時間をかけて故人を偲びたいと思う方もいるでしょう。後悔のない直葬にするには、そのような方々からの理解を得ることも重要です。直葬後に、「お別れ会」と称して改めて惜別の機会を設けるなど、参列希望者への配慮も忘れずに行いましょう。
2-1. 心を込めた直葬を執り行いたいときは?
直葬に対する不安点として、「周囲の理解を得られない」というものがあります。確かに、「直葬はあっけない。もっとしっかりとご供養してあげないと寂しい」と感じる人の気持ちもよく理解できますし、むしろ当然ともいえるでしょう。「まごころ完結葬」では、そのような故人への想いを大事にした直葬が行えるよう、お手伝いをしております。手配した僧侶により戒名の授与や納骨、七回忌までの法要などを行い、心を込めて故人様を供養します。
3. 直葬を執り行う際の注意点
直葬にはメリットがありますが、実際に執り行う際は注意点も考慮する必要があります。その中でも「知らなかった」では済ませられない特に大事な注意点を3つ紹介します。
3-1. 遺体の安置場所を確保する必要がある
火葬を行えるのは「死亡診断書」に記載された死亡時刻から24時間が経過してからと法律で定められています。病院では長時間の安置をしてもらえないので、臨終してから火葬場へ搬送するまでの間、故人を安置しておく場所を自分で用意する必要があります。さらに、火葬場は予約制のため、24時間後もすぐに利用できるとは限りません。場合によっては数日間の安置が求められます。
安置場所は自宅でもかまいませんが、数日間の安置となると何かと不安もあります。その場合は葬儀業者や火葬場に連絡して、霊安室を使用させてもらいましょう。
安置場所は自宅でもかまいませんが、数日間の安置となると何かと不安もあります。その場合は葬儀業者や火葬場に連絡して、霊安室を使用させてもらいましょう。
3-2. 葬祭料・埋葬料を受け取れないケースがある
葬儀による遺族の経済的負担を減らすために、健康保険組合や自治体から葬儀費用の一部が埋葬料として返ってきます。この返還されるお金を、故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合は「葬祭費」、国民健康保険以外の被保険者だった場合は「埋葬料」といいます。
これらのお金を受け取るには、葬儀を行ったという申請が必要です。しかし、直葬の場合は「葬儀を行っていない」と判断されて、返還されないケースもあります。申請が通るか否か不安な場合は、健康保険組合や自治体に事前に確認してみましょう。
これらのお金を受け取るには、葬儀を行ったという申請が必要です。しかし、直葬の場合は「葬儀を行っていない」と判断されて、返還されないケースもあります。申請が通るか否か不安な場合は、健康保険組合や自治体に事前に確認してみましょう。
3-3.菩提寺への連絡
菩提寺やお世話になっているお寺がある場合は、直葬を行うことを事前に報告するようにしましょう。一般的な葬儀でも同じですが、特に直葬の場合は、お寺への報告を忘れてしまいがちです。無断で葬儀を済ませてしまうとお寺との関係がこじれて、お墓への納骨ができなくなるケースもあります。今後の供養のことも考えて、菩提寺には事前にきちんと報告するようにしましょう。
4. 直葬における喪主側のマナー
直葬は少人数・小規模で行うとはいえ、故人をお見送りする厳粛な儀式の場です。いくつかのマナーを守る必要があります。
4-1. 身内のみの参列でも黒色の服を着る
身内しか参列しない直葬だとしても、葬儀にふさわしい服装を選びましょう。紋付きの和装やモーニングコートなど、一般的な葬儀のようにきっちりとした喪服を着る必要はありませんが、最低限、黒色のスーツを身につけるようにします。
4-2. 香典を受け取ったら返礼品を用意する
直葬でも香典をいただいたら、一般的な葬儀のように返礼品を用意します。返礼品の相場はいただいた香典の金額の3分の1〜半額です。
返礼品を用意するのが難しい場合は、直葬を行う前に「香典は不要です」と参列者に通知しておきましょう。
返礼品を用意するのが難しい場合は、直葬を行う前に「香典は不要です」と参列者に通知しておきましょう。